愛を叫ぶマリモの「ほどほどプレッパー入門」
~笑って備えて、平常心~
こんにちは、マリモです。
星の数ほどあるブログの中から、この小さな島のようなブログに来てくださって、ありがとうございます。
本ページはアフィリエイトプログラムを利用していますが、「備えよ常に」を押し売りするつもりはございません。
今日は「防災」よりも少し肩の力を抜いた「減災」のお話です。
ほどほどに備える人(プレッパー)が増えるほど、混乱が起こりにくくなるんです。
1.ある日、マリモは夢を見た

舞台は水浸しの道路。
腰から下は水にジャブン…そして大切なスマホは水没。
現実ではあり得ないほど冷静な私は、斜め45度上空から「わたし」を観察していました。
(※夢なのにカメラアングルが妙に凝っている)
で、この夢から目覚めたときの私の感想は…
1 なんて怖い夢をみたんだろう、早く忘れよう
2 何か意味ありげな夢だなぁ、ここから学べることは?
正解は2。
だって、こういう記事を書いてる時点でお察しでしょ。
2.スマホが使えなくなると…?
もしスマホが使えなくなったら…を想像してみました。
* 家族の電話番号すら覚えていない
* 地図はGoogle頼み
* 支払いはほぼキャッシュレス
* 大事な写真も全部スマホの中
* エンターテイメントの喪失
* アプリの利用不可
つまり、スマホが沈没したら私の生活も沈没。
これ、ちょっと笑えない。
だから思ったんです。
「アナログの私よ、帰ってこい」って。
- 家族の携帯電話番号は暗記する。
- メモ帳に、重要な連絡先・パスワードなどを記入して覚書とする。
- 写真は自動的にバックアップする機能を使う。
- 普段から自然を観察して、天気を予想してみる。
- 手元にある程度の小銭を用意しておく。
- 紙の地図を用意しておく。
このようにして、「もしスマホが使えなくなったら」と想像することで、次第に減災意識に目覚めることになるのでした。
と言っても、スマホがない時代を半世紀生きてきたわけですから、昔はどうしていたかなぁと思い出せばいいのですけどね。(笑)
3.減災って知ってます?
防災は「全部守るぞ!」という完璧主義な考え方。
でも、東日本大震災など大規模な災害では、被害を完全に防ぐことは不可能で、想定される全ての被害を食い止めようとするといくら コストをかけても間に合わないことが明白となりました。
そこで「減災」。災害時に発生する被害を最小限に抑えるための取り組みです。
被害をゼロにするんじゃなくて、人命が失われるという最悪の事態だけは 何としても避けようという発想が生まれたのです。
プレッパーたちの知恵も、この減災の発想に近いんです。
プレッパーから学ぶ「ほどほど備蓄」
アメリカの連邦緊急事態管理庁(FEMA)は、以前は72時間分の備蓄を推奨していましたが、今は「できれば1週間分」に変更。日本政府も同じ考えです。
参考までに、東日本大震災で復旧にかかった期間は、電気1週間、水道3週間、ガス5週間と言われています。
でも、家中を非常食と水で埋め尽くす必要はありません。
おすすめは「日常の延長でストックして回す」方式。
いつものご飯+ちょっと保存性高めバージョン、がちょうどいい。
マリモ基準おすすめ非常食
- 保存水(できれば1週間分)
- アルファ米(白米・お赤飯・五目ごはんなどバリエーション豊富)
- 缶詰(ツナ・サバ・フルーツ)
- 栄養バーや羊かん(非常時の甘い癒やし)
- 調味料(塩・砂糖・味噌は心の支え)
アルファ米は水でも戻せる優れもの。お湯なら15分、 水なら1時間。
災害時の「待ち時間」がちょっとした瞑想タイムになるかも。
週末減災生活
週末は家族を巻き込んで「非常食 お試し会」がおすすめ。
乾パンをかじって歯が欠けそうになったら、それはそれで笑って改善すればOK。
慣れておくことで、非常時のストレスは確実に減ります。
作ってみた「干し飯」
炊いたお米を天日干しして カリカリに。
最長 20年保存できるらしいけど 3日間 ベランダで見張る必要があるので、途中で「何してるんだろう 私…」と哲学タイ厶に入る可能性あり。
結論: 市販のを買った方が早いし、安全。
🌾安心米で、笑って備える
出雲国の非常食、お守りにいかがですか?
4.やり過ぎ?プレッパー
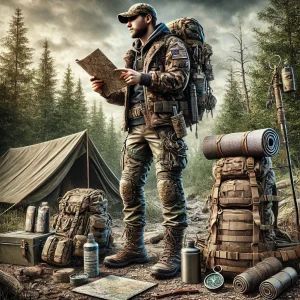
「備えあれば憂いなし」There's no need to worry if you're prepared
本格的なプレッパーは、最悪の事態に備えて非常食や日用品、武器などを備蓄しています。
これまでは地球平面説を唱える人々と同じように、大げさと見られてきました。
しかし、21世紀になり、災害やテロ、はたまた 流行り病など多様な危機を抱えるマルチハザード時代の到来といわれる中で、プレッパーたちの行動から学べることは多いことがわかってきました。
以下、プレッパーが一般的に備蓄しているものの一部をご紹介します。
1. 食料品
長期保存可能な食品:缶詰、乾燥食品(米、パスタ、豆類など)、フリーズドライ食品など
非常食:エネルギーバー、保存水、栄養価の高いインスタント食品
調味料:塩、砂糖、オイル、スパイスなどの基本的な調味料
2. 飲料水
飲料水:少なくとも3日分、理想的には1週間以上の飲料水を確保
浄水器:川や池などから水を得るためのポータブル浄水器
3. 医療用品
救急キット:包帯、消毒液、絆創膏、基本的な医薬品(鎮痛剤、抗生物質など)
常備薬:必要に応じた処方薬やサプリメント
4. 生活必需品
衛生用品:トイレットペーパー、石鹸、歯磨き粉、生理用品、非常用トイレなど
ライト:懐中電灯、ランタン、予備の電池、ソーラーチャージャー
暖房器具:ブランケット、薪、ポータブルストーブなど
5. 防衛用具
自己防衛アイテム:ペッパースプレーや自己防衛用の道具
サバイバルナイフ:多機能で使えるナイフ
6. エネルギー源
ポータブル電源:ソーラーパネル付きのバッテリーや発電機
燃料:プロパンガス、ガソリンなどの燃料
7. 重要書類のコピー
個人情報の保管:パスポート、保険証書、銀行情報などのコピーを防水ケースに入れて保管
8. その他のツール
多機能ツール:レンチ、スクリュードライバーなどの基本的な工具
ロープやテープ:テントやシェルターを作るために使える
彼らは、これらの備蓄を定期的に確認し、古くなったものを更新することで、常に使える状態を保つように努めています。
「備えあれば憂いなし」という精神で、彼らはどんな状況にも対応できるように日々、準備を整えているのです。
極端なほど備える彼らの行動をそのまま真似しなくても、ほどほどプレッパーになりたいものですね。
現在、いろいろな配信者が備えるための動画を配信していますので参考にするのも良いでしょう。
マリモ調べでは、そのような配信のコメント欄に注目、実際に大きな災害にあった当事者の方が書き込んでくださることもあり、そうした生きた情報はとても参考になります。
そのほか、何をそろえていいか迷った時は…
海外旅行に行くとしたら、どんなものを持っていくかを考えてみるといいそうです。
たとえば、処方薬は海外では調達できないから準備しておこう、そういうイメージで必要なものを一つ一つそろえていくのがいいです。
5. 心の備えも忘れずに

「不安より想像力」
最後にマインドの話をします。よく心の準備をしましょう と言いますが どんな心の準備をすればいいのでしょうか。
「怖いから備える」より、「これがあると安心♪」で備えるほうが冷静さもアップ。
ご近所さんのことまで想像できたら、もうあなたは立派な“ご近所プレッパー”。
最大の過ちは 災害に対して全く備えをしないことです。
この記事を書いている 2024年8月21日現在 、南海トラフ地震臨時情報に伴う注意の呼びかけは終了したようです。
ですが、引き続き備えは必要ということで、
一時は水やトイレットペーパー、 最近では米の買い占めが起き、非常用トイレなど備蓄品全般への関心も高まっているようです。
これまではやり過ぎプレッパーを見るような目で「大げさだなぁ」と言っていた家族も、今回のことがきっかけとなり、がぜん協力的になりましたので、週末は減災意識を高める行動に巻き込んでいるというわけです。
![]()
恐い気持ちもわかります。わかりますが、このようなマインドだと、焦りやパニックが邪魔して、いい発想がわいてきません。
そして、ここがいちばん伝えたいことですが、ほどほどに備えることで心に余裕が生まれ、想像力や問題解決能力がさらに高まるということです。
つまり 、楽しく備えるなんて不謹慎だと思うかもしれませんが、いざという時にも冷静に判断して行動できる自信が生まれるものなのです。
さらに付け加えると、自分や家族だけでなく、「友人や近所の人のためにも何かできることはないかな」と考え始めると、いろいろなアイデアや発想が広がりますよ。
それでは、ほどほどに備えが整ったら、あとは余計な心配や不安に駆られず、ゆったりとリラックスして日々をお過ごしください。
あなたの大切な時間を使ってお読みいただきありがとうございました。
