星の数ほどあるブログの中から、当ブログにお越しくださりありがとうございます。「老化もまた進化」を合い言葉に明るく生きるためのヒントを愛を込めて綴ります。
あなたは「防災」と「減災」の違いがおわかりでしょうか。
「防災」は、あくまで被害を出さないために まんべんなくコストをかける発想で行われていました。
しかし 東日本大震災など大規模な災害では、被害を完全に防ぐことは不可能で、想定される全ての被害を食い止めようとするといくら コストをかけても間に合わないことが明白となりました。
一方、「減災」とは、災害時に発生する被害を最小限に抑えるための取り組みです。
被害をゼロにはできないものの、被害を減らすために限られた予算や資源を効果的に活用することで、結果的に被害の最小化を図ろう、人命が失われるという最悪の事態だけは何としても避けようという発想が生まれたのです。
あの日の記憶とは東日本大震災の記憶のこと。この日から減災意識が芽生えたのは間違いありません。
今、もし急に大地震が発生したとして、あなたがいるお部屋は安全ですか?断水や停電になっても困らない用意はありますか?
改めて日頃からの備えを確認するとともに、災害への備えについて、家族や身近な人と話し合ってみませんか。
私たち一人ひとりが 減災意識を持って取り組めば 大難が小難に、小難が無難になる可能性が広がると信じています。
備忘録
ここで備忘録として、東日本大震災の時のことを書いておきます。被災地の被害には遠く及びませんが。隣県住まいですから、少なからず被害はありました。
桜がきれいだった時期なのに楽しむ心の余裕などまったくなくて、ひたすら"見えない敵=放射能"の恐怖で呼吸も浅くなりました。
スーパーやコンビニの棚から水や食料が消えた光景、ガソリンスタンドへの車の大行列も忘れられません。
揺れがおさまってしばらくして我に返った頃、水道が使えないことに気づきました。コンビニに行くと水はすでに売り切れていました。かろうじて氷が残っていたので即購入、溶かせば水です。
家にカセットコンロとカセットガスの備蓄があり、しばらく圧力鍋で蒸し煮をつくって食べました。非常時に圧力鍋は強い味方です。少量の水でお肉も野菜も一緒に調理できます。水と加熱時間とガスの節約になります。
圧力鍋は大きくて普段使いませんが、あの日の記憶が捨てないでと言うもので…
塩とオリーブオイルをかけるだけでシンプルで美味しい一品が出来上がります。家族みんなのお気に入りになりました。何はなくてもお腹を満たすことは重要だと感じました。
幸い、冷凍庫には食材がギッシリ詰まっていました。とても助かりました。今でも冷凍庫はギッシリ詰めています。隙間なく詰めた方が効率的に冷え、省エネになります。
逆に、冷蔵の方はスカスカです。食材を詰め込み過ぎると、冷気の循環が悪くなり、庫内を冷やすために余分なエネルギーが必要になるそうです。
また、冷凍食材を冷蔵庫に移して ゆっくり解凍する時にもスペースがあると何かと便利です。
困ったのは生活用水
困ったのは、飲み水というより生活用水でした。「“生活用水”が圧倒的に足りなかった」と実際に災害を体験してみて気づいたんですよね。生活には思いのほか大量の水が必要なのです。
ポリタンクを持参し、給水場所に指定された公園で並び、自衛隊の方々に水を入れてもらいました。その重いポリタンクを何度も運ぶのが大変でした。いざという時、エレベーターを使えないことを考えると、マンションは5階が限界だと思いました。
今は、空いたペットボトルに水道水を入れたものを何本か用意して定期的に交換していますが、充分とはいえません。課題の一つです。そこで 少し調べてみました。
💡ちょっと昭和な生活用水の備え方
【水道水のペットボトル備蓄は“回転備蓄”で】
今マリモがやってる苦肉の策。空いたペットボトルに水道水を入れて時々交換。浄水ではなく水道水をおすすめします。
たとえば、月はじめにはひと月分の水を洗濯などで使い切って、新たに水を入れておきます。500ml から 2 L サイズ まで数本 用意しています。
【折りたたみ式ウォータータンク】+【キャリーカート】
ポリタンクの代わりに「折りたたみタイプのウォータータンク(10L〜20L)」を用意。蛇口付きが便利。普段から水を入れておき定期的に水を交換。
非常時にはキャリーカート(台車)に乗せて運べば腕力いらず!また、🔍「ウォータータンク キャリー付き」で検索するといろいろな商品があります。コロ付きのウォータータンクも気になります。
お手持ちのポリタンクに水を入れる場合、いざ使う時や水交換の時に重くて腰がやられます。そんな時の強い味方が手動ポンプ、灯油ストーブに使うアレです。
アレ=灯油ポンプというらしいです。そのまんまでした。水専用に1本用意しておくと安心です。100均にも売ってます。
余談 手動ポンプで1つ 思い出したことがありました。昭和のお話です。
実家にはいくつか水槽があって 熱帯魚を飼っていました。 水槽の水を取り替える時、父はホース 1本で汚れた水を汲み出したのを覚えています。高低差をつけるのがコツです。まず ホースの片方を水槽に入れ もう片方は自分の口で思い切り吸うんです。(@_@;)
すると面白いようにバケツに流れ出てくるのです。間違って汚い水を飲んでしまう危険性もあり、今では衛生面を考えるととんでもないかもしれませんが、昔はそうしていました。
どこかで使える技なのか、できれば使いたくない技です。今は亡き 優しい父の記憶を添えて。
【浴槽の水をためておく】
地震後すぐ断水するとは限らないので、揺れがおさまったらすぐに水を確保するといいです。浴槽、バケツ、シンク等にできる限り水をためましょう。
普段からお風呂の残り湯を抜かずに置いておくだけでも心強いです。※ただし、衛生面に不安がある場合は“洗濯・トイレ流し用”と割り切って使うのがコツ。
ちょっと思いついたのは、あまり 現実的ではないかもしれませんが、お風呂に入った後に水を捨てさっと洗い流し、新しい水を浴槽にためるというのはどうでしょうか。
これなら一応きれいな水として用途が広がりそうです。何もなければ沸かしてお風呂に。
【非常用トイレ(携帯トイレ)の活用】
マンションなど集合住宅の場合、地震によって排水管の破損の恐れもあるため、安易に水を流すのは避けたいところ。水を使わない想定で「非常用トイレ」の備蓄は必須です。生活用水の節約にもなります。
【雨水タンクの導入(戸建て向け)】
戸建てにお住まいなら、雨樋に接続する「雨水タンク」の設置もありです。ガーデニングや災害時のトイレ用水として使えますし、自治体によっては補助金が出ることも。
🌼ちょっとした工夫
ウェットティッシュやおしりふきの備蓄。お風呂に入れない時の身体の拭き取り用として大判サイズがあると重宝です。
使い捨ての紙皿やラップで食器を覆い、洗い水を節約。水の使用は極力避けるアイデア、もうご存じですよね。
もっといい方法がたくさんあると思います。知りたいと思ったところにこんないいサイトがありました。
経過時間によって実践できる知恵がまとめられています。被災直後〜24時間・24時間〜72時間・ 72時間〜と3段階にカテゴリー分けされていてわかりやすいため、お子さんと一緒に確認するのも良さそうです。
普段からも使えそうな知恵も盛り沢山ですよ。たとえばこんなことが載っています。
揺れがおさまったら
段階的に確認して安全に避難しよう。まずは自身にケガ等がないか、割れたガラス・がれき等転倒や足元を傷つけるおそれのあるものがないかを確認します。
そのあと、火元の確認をし、電源ブレーカーを落として安全な避難を開始します。
また、建物から脱出する際は、慌てて外へ飛び出してしまうと大変危険です。屋根の瓦や窓ガラス、看板等、落下物や破損物の被害に遭わないよう、周囲の状況をよく確かめて、落ち着いて行動することを心掛けましょう。
連絡手段について
大きな災害が起きると、被災地への音声通話の集中により、通信回線が非常に混雑します。東日本大震災でも平常時の数十倍以上の通話が一時的に集中し、長時間に渡りスマートフォンや携帯電話がつながりにくい状態となりました。
災害等の緊急時に有効となるのが公衆電話。NTTが設置する公衆電話は、通信規制の対象外として優先的に取り扱われます。
これは「災害時優先電話」といわれ、通常の電話よりもつながりやすくなっているため、いざというときの連絡に役立てることができます。
ただし優先電話は、あくまで「優先」して扱うものであって、電話が必ずつながることを保証するものではありませんので、あらかじめご注意ください。
また、公衆電話の設置数は年々減少しているため、公衆電話が見つからない、もしくは長蛇の列ができる可能性があります。(普段から散歩がてら 公衆電話を見つけたらメモしておくのもいいですね)
また、スマートフォンや携帯電話のメール、SNSへの書き込み等を活用し、連絡の取りやすい手段を試みる場合は、長文・大量のメールは避け、手短な文面を心掛けましょう。
なるべくスムーズに連絡を取り合い、不安な気持ちを少しでも和らげましょう。
災害用伝言ダイヤル171の活用法
「災害用伝言ダイヤル」とは、大規模災害によって被災地への電話が増加し、つながりにくい状況になったときに提供が開始される伝言サービスです。
固定電話、携帯電話等から「171」をダイヤルすることで、利用ガイダンスに沿って伝言の録音・再生を行うことができ、家族や身近な人との間での安否確認、避難場所の連絡等をすることができます。
この災害用伝言ダイヤルは、毎月1日・15日の00:00~24:00、
正月三が日(1月1日00:00~1月3日24:00)、
防災週間(8月30日9:00~9月5日17:00)、
防災とボランティア週間(1月15日9:00~1月21日17:00)に体験利用できます。
帰宅困難者になった時の心構え
災害時帰宅支援ステーション
コンビニ、ファーストフード店、ファミレス やガソリンスタンドが拠点になっていることが多く 店頭には ステッカーが貼ってありあるので知っておくと便利です。
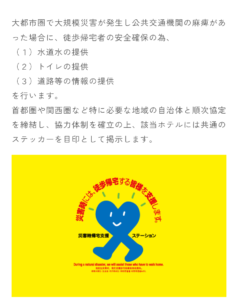
安否確認・張り紙の活用
一緒に暮らす家族や、身近にいる人と離れ離れのまま、避難を余儀なくされた場合は、自宅や避難所等に安否を知らせるものを残しましょう。
「避難しました」等の張り紙をすることで、家族の捜索を効率的に行えます。自宅から避難する場合は、あらかじめ決めておいた場所に張り紙を残しておきましょう。
自分や家族の安否情報、避難先等を記した張り紙を残すことによって、ほかの家族が自宅に戻った際に、家族の安否や居場所を知る手掛かりになります。
ただし、避難を知らせる張り紙は、居住者の不在を知らせることになりますので、家族であらかじめ話し合っておいた人目につかない場所に張り紙をしてください。
メンタルケア
不安が頭から離れず、眠れない。そんなときは、頭を手のひらで優しく包み込んであげます。頭をもみほぐしながら、心身を徐々にリラックスさせていきましょう。
不安なことが頭から離れなくなってしまうときは、できるだけ楽しいことを考えるようにしましょう。好きな人や食べ物、楽しかった旅行の思い出、友人とのくだらない会話等、ゆっくりと風景や情景等の細かい所まで思い浮かべると、自然と意識が遠くなり、眠りにつきやすくなります。
先のことを考えると不安な気持ちが大きくなりやすいので、なるべく楽しかった過去のことを思い出してみてください。
もし、風景や情景等を思い浮かべるのが難しいときは、本があると心強いです。避難グッズの一つに加えるといいかもしれませんね。心身をリラックスさせ、不安の軽減につなげられそうな1冊。ピンときたらそれを。
マリモは「あなたの牛を追いなさい」枡野俊明さん松重豊さんの本がピンときました。
減災対策「備えあれば憂いなし」おすすめ記事もぜひご参照ください。
あの頃から10年以上経って感じるのは、家族が元気なこと、新鮮な空気を胸いっぱいに吸い込み深呼吸できること、綺麗な花が綺麗だと思える心の余裕、これこそが幸せなんだという気づきです。
その幸せに感謝しながらも、明日来るかもしれない非常時に備える減災意識を忘れなきようお願いしたいと思います。
備えが希望にもなりますように🌿
あなたの大切な時間を使ってお読みいただきありがとうございました。
